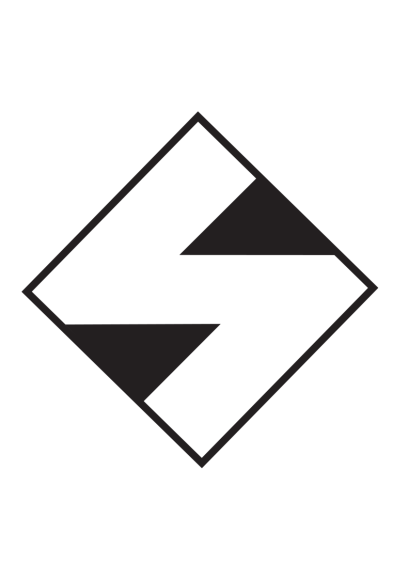機械を止めない工夫
“できない”を言わず自ら考える文化が技術を磨く
祖父の技術から始まった町工場
有限会社柴田製作所 NC旋盤、複合旋盤、マシニングセンタを用いた部品加工
柴田浩志

- 都道府県
- 愛知県
- 事業内容
- NC旋盤、複合旋盤、マシニングセンタを用いた部品加工
- 会社名
- 有限会社柴田製作所
- 代表者名
- 柴田浩志
- 所在地
-
〒483-8242
江南市五明町根場273
- 電話番号
- 0587-56-2857
- ホームページ
Factory Stories
祖父の技術から始まった町工場
柴田製作所は三代目社長・柴田浩志の祖父、柴田三雄が1955年に創業した。
「戦時中に大阪で砲弾を削っていた技術を生かして金属加工の仕事をはじめたそうです」
当時はあまり設備投資もできなかったため、ボール盤で穴あけをするなどの簡単な加工がメインだったという。
1981年には浩志の父、柴田学とその弟(浩志の叔父)が三雄の仕事を引き継ぐことになり、法人化も果たした。
単能機を導入して軸物の端面削りなどをやるようになり、その後、旋盤・ロボドリルやマシニングを導入して仕事の幅を広げていった。
これにより、横穴開けやDカットなどの付随加工は社内で完結させられるようになった。
当時は、ひとつの工程に特化している工場が多かった中、「シャフトの先端にピン穴を付けてほしい」などの顧客からの複数加工の要望に応えていったのだ。
機械を止めるな!効率化の知恵
当時の柴田製作所の一番の強みは『速さ』だった。
時代背景に後押しされたこともあり、仕事の幅を広げた柴田製作所への仕事の依頼は後を絶たなかった。
そのため、速さを実現するために機械を止めずに加工をする工夫を凝らしたのだ。
「機械が加工している時間は人間のやることはありません。対面にもう一台置けば振り返るだけだから、一人最低2台は見られる……と、レイアウトを変えたんです」
柴田製作所の仕事は中小ロットの小物がメインで個々の加工時間が短いため自動化することは難しい。
しかし、一人の社員が複数の機械を見られるように工夫を重ね、ベテランならば3台、4台同時に動かせるようにしたのである。そして、この方法は現在でも続いているという。
「新人だと2台任せても両方の機械が止まってしまうことがあります。でも、慣れてくると片方が動いている間にもう片方を取り換えることができるようになりますよ」
裁量あるものづくりが技術を育てる
柴田製作所の働き方にはもう一つ特徴がある。
それは社員にある程度の裁量を与えて、自由に改善提案ができる文化だ。
浩志自身が仕事の中で楽しいと感じるのは、思い通りにできないものを試行錯誤する中で作り上げられることだという。
そしてうまくできるようになったら、どこを工夫すればもっと速くなるか、もっとコストを抑えられるかを考えることが楽しいという。
この浩志の感じる楽しさをすべての社員が得られるようになっているのだ。たとえば、利用する刃を変えることで効率が良くなると思ったならば、工具商社に相談し、時間短縮やコストなどを算出して自ら提案することができる。
「ボタンを押すだけじゃ楽しくないですよね。それに自分で考えて工夫することで技術力も上がります。その技術力は社員ひとり一人の財産なので、もしも他の工場で働くことになっても恥ずかしくないくらいの技術はみんな持っていると思いますよ」
社員一人ひとりが自主的により良い方法を考える。
もしも行き詰まったときには仲間と相談し、どうにもならないときに社長に相談するという流れができているのだ。
「でも、僕が答えを出すことはありません。普段から加工をしている社員の方がよくわかってますからね。僕は話を聞きながら、問題がどこにあったのかを見つけるきっかけを作っているだけです」
三代目が挑んだ“現場改革”
社員全員に裁量を与える方法は、浩志が取り組みはじめたことだ。
先代が指揮していた頃は、プログラムができる数名が中心となり、他の社員はサポート的な役割を担っていた。
先代のやり方を変えることを選んだのは、浩志が三代目社長に就任することがわかっていたからだ。
「僕は父や叔父が管理していた内容を知らなかったんです。いつか現場を離れたとき、僕一人で管理するのは不可能ですからね」
そこでサポートを担当していた社員たちに、業務のノウハウを伝えていくようにしたのだ。
そうして、2022年に浩志が三代目社長に就任した頃には、全社員が自らの裁量で考えながら仕事ができる体制になったのだ。
後継ぎを決めた父への感謝
浩志は幼い頃から、日が昇る前から夜遅くまで働く父親の姿を近くで見てきた。
中学生や高校生の頃には、アルバイト代わりに工場の仕事を手伝っていた経験がある。
そのため、金属加工の仕事は生活の中に当たり前にあるものだと感じていたという。
「僕は三人兄弟の末っ子ですけど、大学にも行かせてもらえましたし、海外のホームステイにも行かせてもらえました。だから父には本当に感謝しているんです。父は継がなくても良いと言ったんですけど、僕はこの仕事をしようと決めました」
そうして大学卒業後、2年ほど自動車部品の設計の仕事をしたのち、絞り加工の試作メインの工場に修行に出て加工の技術を学んだ。
そこでプレス絞りやレーザー加工、ワイヤーカット、マシニングから金型設計までを経験したという。
“できない”と言わない見積からはじまる挑戦
浩志の修業時代の経験は、現在の柴田製作所の強みにもなっている。様々な加工方法を知っているため、多方面から加工のアプローチを考えられるのだ。
自社でできない加工でもアドバイスをすることができ、目的を達成するための道筋を提案することができる。
さらに、裁量を持たせたことで社員一人ひとりの技術も向上している。
「今は、難易度の高い仕事も『できない』と言わず見積を出しているので、以前よりも難しい加工の依頼が増えていますね」
未経験の加工でも見積を出し、依頼が来れば試行錯誤しながら仕上げていく。
それがさらなる技術の向上につながるのだ。
「やったことのないものだと、結果的に見積額を超えてしまうこともあります。でもそれは投資なんですよ。フィードバックして次に生かしていくことでさらに色々な加工ができるようになりますからね」
社員が“時間とお金”の両面で豊かになれる会社に
浩志はこれから先の柴田製作所を、社員が時間とお金の両面で豊かになれるような会社にしたいと考えている。
これは、浩志がホームステイ先のヨーロッパで働く人々を実際に見て来たことで抱いた想いだ。ヨーロッパでは、定時で仕事を終えて、すぐに家に帰って家族との時間を楽しんでいる。
「工場は機械を動かさなければお金になりません。だから必ず会社に来なきゃいけないんですけど、10時間も12時間も集中して働くのは無理ですよね。だから、短い時間でいかに生産性を上げるかが大事だと思います」
また、モノづくりの価値をできるだけ多くの人に知ってもらいたいとも語った。
一般の人は完成品を目にしても、そこにどれだけの工夫や技術、労力がかかっているのか理解することができない。その製品を生み出すための見えない部分の価値をもっと知ってもらいたいという。
そのひとつとして、自社ブランドの製品をつくることも考えている。
「うちの加工技術を生かしてメーカーになれたら、さらに楽しい仕事ができるんじゃないかと思うんです」
柴田製作所は、理想を実現するために、社員たちと力を合わせてさらなる挑戦をしていくのだろう。